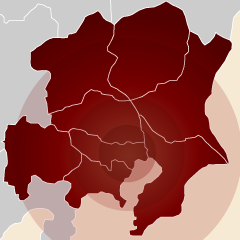前の職場から同僚・部下を引き連れて独立するのは違法? 引き抜きをした従業員の賠償責任を解説
不動産、建設、コンサル、学習塾をはじめ多くの業界では、いったん会社に勤めて経験やノウハウを培ったうえで、いざ同業種で独立起業を果たすという社員・従業員がいます。
このような独立起業を行う場合、独立をする従業員としては、一から面識のない方を対象に採用活動をするよりも、職場の同僚や部下などの見知った仲にある方を勧誘して雇ったほうが能力や相性等の面でリスクを下げられると考えられ、一緒に独立しようと試みることも多いでしょう。
もっとも、従業員が他の従業員を引き連れて独立起業することは、前の職場からみれば会社の資産と言うべき人材が奪い、損害を与えてしまう行為になりかねません。
そのため、このような独立起業時の引き抜き行為は、しばしば前の職場との間でトラブルの火種になり、従業員が前の職場から損害賠償を求められるという事態に発展します。
本コラムでは、このような前の職場から同僚や部下を引き連れて独立起業する行為がどのような場合に違法となるのか、どの程度の賠償を負うことになりえるのかを解説します。
1.ポイント①:違法になるのは基本的に在職中の引き抜き行為
(1) 在職中は会社の利益を不当に侵害しない義務を負う
まず押さえておくべきポイントは、違法になるのは基本的に在職中の引き抜き行為であるということです。
従業員の引き抜き行為の違法性について判断した裁判例は数多くありますが、英会話教室の従業員の引き抜き行為が問題とされた東京地裁平成3年2月25日判決は、次のような義務を根拠に、引き抜きを図った従業員に賠償を命じました。
「会社の従業員は、使用者に対して、雇用契約に付随する信義則上の義務として、就業規則を遵守するなど労働契約上の債務を忠実に履行し、使用者の正当な利益を不当に侵害してはならない義務を負い、従業員が右義務に違反した結果使用者に損害を与えた場合は、右損害を賠償すべき責任を負う」
他の裁判例の多くもこのような見解を前提に判断を下しています。
そのため、就業規則などで従業員の引き抜き行為が明確に禁じられている場合は当然として、就業規則などでこのようなルールが定められていない場合でも、引き抜きを行った従業員には賠償責任を認めることがありえます。
(2) 退職後は基本的に引抜行為は違法にはならない
一方、この使用者(会社)に対する義務は雇用契約に付随する義務であるため、雇用契約が終了した後、すなわち退職後にはなくなります。
したがって、従業員が退職後に引き抜きを行うことは基本的には違法になりえません。
ただし、退職時に引き抜き行為を禁止するような合意をしている場合には、その合意が適法な内容である限り引き抜きをしない義務を課されることになるため、合意に抵触するような引き抜きは違法になりえます。
また、裁判例の中には、使用者に損害を与える目的で従業員を一斉に退職させて会社の組織活動等が機能しえなくなるようにするなど、「社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様」でされたものについては違法性を肯定しうることを示唆したものもあり(東京地裁平成6年11月25日判決等)、退職後の引き抜き行為が絶対に違法にならないとまでは言えないと考えられます。
2.ポイント②「部下同僚への勧誘=違法な引き抜き」ではない
(1) 単なる転職の勧誘は違法ではない
次に押さえておくべきポイントは、部下や同僚への勧誘をした場合でも直ちに違法な引き抜きとされるわけではないということです。
一般的に、個人の転職の自由は最大限に保障されるべきであるという観点から、従業員の引抜行為のうち単なる転職の勧誘に留まるものは仮に幹部従業員によるものであったとしても違法とはいえないものとされています。
(2) 違法か適法かはどのような基準・事情で判断されているのか?
勧誘を行う場合でも、独立する従業員は、退職時期を考慮したり、事前の予告を行うなどして会社の正当な利益を侵害しないよう配慮すべきとされています。
そのため、これをしないばかりか会社に内密に移籍の計画を立て一斉、かつ、大量に授業員を引き抜く等、その引抜きが単なる転職の勧誘の域を越え、社会的相当性を逸脱し極めて背信的方法で行われた場合には、それを実行した会社の幹部従業員は雇用契約上の誠実義務に違反したものとして、債務不履行あるいは不法行為責任を負うものとされています。
社会的相当性を逸脱したか否かに関して裁判所が重視している事情としては、転職する従業員のその会社に占める地位、会社内部における待遇及び人数、従業員の転職が会社に及ぼす影響、転職の勧誘に用いた 方法(退職時期の予告の有無、秘密性、計画性等)等が挙げられています。
3.ポイント③:どこまで賠償すべきかはケースバイケース
引き抜き行為について損害賠償を求める場合、損害発生の有無と損害額については、賠償を求める使用者側(元職場側)が立証しなければなりません。
しかし、ここでいう損害とは、基本的に引き抜き行為がなければ得られたはずであるという仮定をした場合の利益ということになります。
このような損害(一般的に「逸失利益」といいます)は、賠償額を証明することは物が壊れた場合の修理費用やけがの治療費のような加害行為や契約違反がなければ生じなかった出費よりも発生したといえるかが不確かであるため、立証のハードルは高くなることが一般です。
現に、裁判例の中には、引き抜き行為が契約違反に当たることを認めながら、損害が立証されていないことを理由に元職場側の請求を棄却したものもあります。(例えば東京地裁平成17年9月27日判決は、引き抜き行為を受けた先物取引の受託を行う会社が、引き抜きに伴って減少した顧客からの手数料収入分について賠償を求めたところ、営業を担当する人員数の増減と手数料収入の増減に相関関係が認められないとして賠償を否定しています。)
そのため、仮に引き抜き行為が明確な契約違反に当たる場合でも、元職場から多額の請求に応じるべきかどうかは、損害とされているものの内容を精査する必要があると言えます。
- 初回相談1時間無料 zoom相談対応
- お電話からご予約いただけます
平日午前9時30分~午後6時30分 03-5817-4001
それ以外の時間帯・土日祝日 050-3695-5322 - メール・LINEでもこちらからご予約いただけます